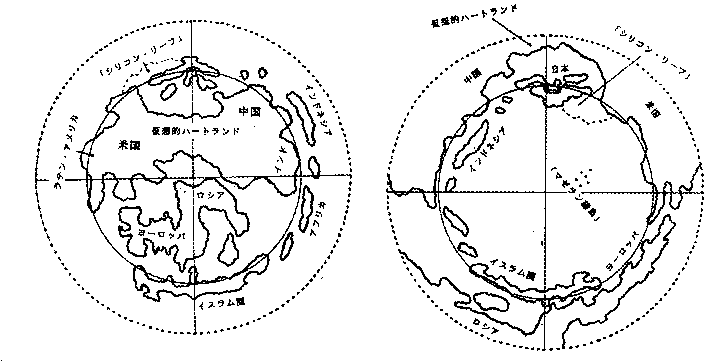 (図は無形化した戦略環境を仮想的な地形として球体に表現した「仮想地球儀」を二方向から見たもの。単に経済力を面積に換算しただけでなく、戦略的に重要な要素は仮想的に地形化してそれぞれ呼び名を与えてある。左図は「陸側」aの観点で見たものであり、右図はちょうどその反対方向からbの観点で見たものである。
(図は無形化した戦略環境を仮想的な地形として球体に表現した「仮想地球儀」を二方向から見たもの。単に経済力を面積に換算しただけでなく、戦略的に重要な要素は仮想的に地形化してそれぞれ呼び名を与えてある。左図は「陸側」aの観点で見たものであり、右図はちょうどその反対方向からbの観点で見たものである。| TOP |
準第4次大戦史研究 長沼伸一郎
この稿は、現在われわれがすでに「準四次大戦の初年度」に突入してしまっているとの見解に従って、その分析を行うものである。
つまり現在の経済戦争を、無形化された数十年間の大戦争の一部と捉え、10年を一まとめにして1年分の戦略的経過に対応させて分析を行っていくわけだが、こうした無形化された歴史を記述するに際しては、現在の新聞はほとんど能力を喪失していると言っても過言ではない。なぜなら本当に重要な事件は無形化領域において起こるというのが現在の趨勢だというのに、新聞やテレビは絵になる大事件が起こったら条件反射のようにそこへ駆けつけてそれをトップ項目に持ってきてしまうからである。
実際、本当に重要な事件が起こっている時にマスコミのトップ項目はしばしばトラックの衝突事故だったり有名人のスキャンダルのことだったりする。そのため現代の市民はかつてソ連の市民が「プラウダ」から何か情報を読み取ろうとする場合にしたのと同じこと−−見出しの一番小さいものから探して読んでいくと、重要な情報を拾い出すことができる−−と似たことを行わねばならなくなっている。
現在のマスメディアは、こうした「絵になる無意味な事件」による撹乱に極めて弱く、強力なフィルターでこうした欺瞞映像を除去できなければ「歴史」の記述ができないのである。そこでここでは敢えて、その「欺瞞映像」を打ち消すために無形化領域の本質を時にやや強引に可視化していくこととする(つまり本筋の部分は「史実」を忠実に記述したものだが、可視化の部分は幾分かの演出を行った「ノヴェライズ」を含む)。
しかしそれについて論じるといっても、何ぶん最終的な結末が判明するのが数十年後のことであるため、まだそれを「歴史」として一冊の本にまとめることは難しい。実際それは、今後数十年にわたって未整理なメモを逐次修正しながら書き続けるしかないであろう。しかしたとえ未整理とはいえどもそれは極めて刺激的なものであるため、現時点で可能な限りの分析と可視化を以下に行っていくこととする。
以下は三つに分かれており
1・準四次大戦の全体的な構図
2・実際の経過(前半)
3・アジアNIES経済電撃戦
1・準四次大戦の全体的な構図
予想される準四次世界大戦の性格
まず、全体的な構図において、それはどんな「戦争」になるのだろうか。まずこれまでの50年間の「準三次大戦」が、第一次大戦に似た動きの乏しい陰欝な膠着状態の戦いであったのに対し、今後予想される「準四次大戦」は、第二次大戦に似てかなりダイナミックで流動的なものになると予想される。そのわけは次の通りである。
まず過去の軍事的戦争のパターンを見た場合、膠着状態であった第一次大戦とは対照的に、次の第二次大戦が極めてダイナミックな戦争になったのは次の理由による。すなわち第一次大戦の膠着状態は機関銃陣地の存在によって生じていたものだったが、その末期に戦車が登場して軍の機械化という動きが起こり、それが最後の局面において膠着状態を打破した。そして次の第二次大戦においては、それを認識した両陣営が機械化されたダイナミックな戦法を最初から採用し、まさしくそれら同士が本格的に衝突したのが第二次大戦だったからである。
これと基本的に同様のことが今回も起こる可能性が高い。つまり核兵器によって膠着状態に陥った準三次大戦の末期に、パワーの無形化という現象が起こってその膠着状態が打破された。そして準四次大戦はそれら無形化されたパワー同士が主力となって本格的に激突する、最初の無形化された大戦争となる可能性が高いのである。
そしてもう一つ重要なことは、これが情報制空権というものが最強のパワーであることが明らかになった上で展開される、最初の無形化された戦争であることで、この点も「偶数番号世界大戦」に共通するダイナミズムを与えると予想される。
準四次大戦のテーマは何か−−世界統合と勢力均衡の最終的対決
では話を元へ戻そう。準四次大戦の全体的なテーマおよび流れがどんなものになると予想されるかは、「無形化世界の力学と戦略」の中でも示唆しておいた。
まずその真の主題は、現在の世界が一つの巨大な世界史的分岐点にさしかかっており、準四次大戦の勝敗がその文明全体の行方を決するものと予想されるということである。その分岐点とは何かと言えば、それは世界が現在その基本構造において勢力均衡型(ヨーロッパ型)と統合世界型(中国型)のどちらを選ぶのかについての決定的な選択を迫られているということである。
過去においては、例えばヨーロッパの場合、ナポレオン戦争の時期に英国とフランスがこの主題を巡って激突し、その時は英国が勝利を収めることで、ヨーロッパは複数の主権国家による勢力均衡型世界であり続けた。また中国の場合、始皇帝の時代にやはりこの激突があり、秦と他の「戦国七雄」諸国の戦いにおいて前者が勝利を収めたことで、以後中国は基本的に単一の帝国による世界となった。そして現在、準四次大戦においてこれと同様の決定的選択が、主として無形化領域において徹底した形で繰り広げられる可能性が高いのである。
陽動と主攻−−二重性の存在
そして現在の世界は、軍事的領域での敵味方と無形化領域での敵味方の関係が互いに矛盾して、一種の二重性を形成する場合が多く、戦略的に見るとそれが主攻と陽動の関係を形成すると予想される。
例えば米中関係は軍事的には敵対関係だが経済的には必ずしもそうではない。この場合米中間の軍事的緊張は、恐らく全体の中ではむしろ陽動の部分を形成し、その裏側で行われるビジネスマンの握手が主攻になる可能性が高いということである。
つまり現在新聞などで論じられているのは、大部分が表面的な可視領域の、どちらかといえば「陽動」の部分だということになる。そしてその背後の真の流れは、無形化領域において、世界統合と勢力均衡の衝突という形で、それとは比較にならない規模で進行中であると見られる。
この巨大な歴史的選択は、過去の他の事件の意義などほとんどけしとんでしまうほど巨大な意味をもったことなのであり、準四次世界大戦こそがその最も決定的な無形化された戦争なのである。
それはどの勢力とどの勢力の対決になるか
ではその二つの勢力を強いて国別に分類した場合、傾向としてどれがそれに属するかはおよそ次のようになるものと見られる。詳しい議論は省くが一応それは
世界統合側−−米国および中国
勢力均衡側−−ヨーロッパ・日本・イスラム
となる可能性が比較的高く、表面的な軍事的対立の背後で、このリーグ間での無形化された激突こそが、真の世界史を形成するものと予想される。それこそが「準四次世界大戦」である。(ただしどの国も必ずしも一枚岩ではないので、完全にこのようにきれいな色分けはできず、どの国も一種の内戦構造を抱えこむことにはなるだろうが。)
戦略面での中心課題−−仮想的ハートランドの存在
その最も重要な戦略の主軸が何であるかという問題は、「仮想的地政学」の領域に入ってくる。一般に過去の英国の地政学においては、内陸部から世界統合を目論む勢力に対して、海洋勢力がいかに勢力均衡を維持するかが、一つのテーマとなっていた。というより英国でマッキンダーがこの学問を作ったとき、もともとは勢力均衡政策をとる側がどうやって生存していくかというテーマこそが、その最大の動機だったのである。
現在の地政学は米国流に読み換えられてこうした意識は希薄になっているが、むしろ今後は無形化された形で、その最大のテーマが再現されてくる可能性が極めて高いと言えるかもしれない。
さて英国の古典的な地政学においては、内陸部に「ハートランド」という領域が生じるかどうかが、一つの大きな鍵になってきた。具体的にはそれはユーラシア大陸の内陸部中枢、つまり東欧からロシアにかけての地域を意味し、そこが単一の帝国に支配されて圧倒的なマンパワーを養うことに成功したとき、勢力均衡世界の終焉が訪れ、世界はその帝国の支配下に置かれるとされた。
そして今回は無形化した形の「仮想的ハートランド」というものが生まれるかどうかが一つの焦点となるものと予想される。それは何かと言えば、米中間に生まれるビジネス・ネットワークこそがその「仮想的ハートランド」に相当するのではないかということである。これが安定して確保された場合、たとえ表面的な軍事的緊張がどうあれ、世界にはその力に対抗できる勢力は理論上どこにも存在しなくなることになる。
そしてもしそうなってしまった時には、「勢力均衡側」は、もはや自分の体質や生存に適したルールや環境を世界の中に作っていくことが不可能となり、一方的にそこに従属しておこぼれにあずかる以外のことはできなくなるはずである。
準四次大戦が世界統合側の勝利で終わった場合の結末−−帝国の出現
実際もし米中が結合した勢力が誕生したとすれば、それは「東西統合新ローマ帝国」とでも呼ぶべき、誰にも抵抗できない巨大帝国の出現となるだろう。
しかしながら将来出現する「帝国」の真の意味は、厳密には多少それと異なるもっと抽象的なものになると考えられる。それはむしろ人類の短期的願望がどんどん肥大して、それが世界中で手をつないでしまったことで生じる仮想的な帝国を意味するのである。
一般に、人間の長期的願望は「理想」と呼ばれ、短期的願望は「欲望」と呼ばれるが、常識的に考えて後者の方が力が強く、前者は圧倒される傾向にある。そのためもし後者の力が前者を完全に駆逐するほどに強く、しかしながら自滅を招く寸前のところでブレーキがかかるという中途半端な状態で歴史が停止し、完全な均衡状態を作ってしまったらどうなるだろう。
それは理屈から言えば、短期的願望が極大化した一番悪いシステムが文明の上に君臨したまま、不治の慢性病のように永久にその状態から抜け出せなくなることを意味するのである(もっともそれが歴史的必然なのだと主張する人も中にはいるが)。おまけに世界中の文明は、それが短期的願望の極大化を目指していくと、どれもこれも自然に形態が似通ってきてしまう傾向があり、その共通性ゆえに手をつなぐとさらにその力が倍加して、復旧をより困難なものとしてしまう。
つまり「短期的願望の極大化」という主題こそが、この見えない帝国の姿なき皇帝の意志なのである。そしてその主題に奉仕しようとする者が世界各国内部に生まれてそれが手をつなぎ、仮想的ハートランドを最大の根拠地として地球全土を覆う単一帝国が出現するというのが、真の意味での「帝国」出現のシナリオである。
「帝国勢」の定義
要するにここで言う帝国とは、何も邪悪な世界支配の意志をもつ国や政府などの集団がどこかにあって、それが征服の陰謀を巡らせているなどということを意味するのではない。むしろ正確に定義するならば、それは「短期的願望の極大化」という一種の仮想的な意志に忠誠を誓い、その力による世界統合効果の一翼を担う者や集団の総称なのである。(この定義からする限り、米国や中国は単にその帝国に協力的なパトロン国に過ぎない。)
もっとも、陸上だけに限定するならば、このように定義された抽象的な「帝国」はすでに圧倒的な存在感をもって君臨しつつあるかに見える。現在、国民国家の垣根を嘲笑するかのように無国籍マネーが暴れ回っているが、これら投機集団はかつてはいみじくも「為替金融帝国」の名で呼ばれていた。(今ではもっと耳ざわりの良い表現で呼ばれることが多いが、それは恐らく一つには、その脅威を指摘していた人がだんだんその中に取り込まれていったためであろう。)
実際これは先ほどの定義に照らした場合、「儲け=短期的願望」の極大化という主題に忠誠を誓う者が世界中で手をつなぐという点で、それを完全に満たしていることがわかる。
なおこれは本来どこの国家にも属さない勢力ではあるが、しかし世界中の国家の中では米国は最もこの「帝国」と親密で、時に同一視されるほどに二人三脚で協調行動をとっているかに見える。そのため一口に「米国のパワー」といっても、そこには米国という国民国家のためのいわば「米国防軍」と「短期的願望の極大化」という仮想的な帝国の意志に忠誠を誓う「帝国軍」の二種類が混在しており、外から見るとしばしば混同されやすいことには注意する必要がある。(後者は本質的に多国籍部隊で、無論日本人も多く参加している。)
準四次大戦の戦略的本質−−エアパワーとシーパワーの死闘
ではもう少し戦略面の分析を絞り込んでみよう。過去の地政学においては、世界の勢力をランドパワー(内陸部の勢力)とシーパワー(海洋勢力)に区分し、第一次大戦の本質をその両者の死闘であると捉えていた。そして過去数十年間の準三次大戦もまた、その本質はソ連を中心とする東側のランドパワーと米国を中心とする西側のシーパワーの間の戦いだったと見ることができる。
では準四次大戦の場合それはどうなるのだろうか。結論を言えば、その本質はエアパワーとシーパワーの間の死闘になると予想される。
まずそれは、最大の中心的プレーヤーである米国の本質が海軍国であるというよりは、より本質的には空軍国であること(さらに中国自体も、ランドパワーそのものというよりややエアパワーに傾斜した口達者な勢力である)を考えれば感覚的に納得できるだろう。そしてエアパワー人種というものは、本質的に「世界は一つ」との台詞を好むものであり、その本性からして世界統合側の中核となり易いのである。
これに対して勢力均衡という概念そのものが、海軍国・シーパワーと表裏一体であることを考えると、むしろ準四次大戦においては空と海の間の死闘という側面がその本質としてクローズアップされてこざるを得ないのである。
「帝国空軍」の台頭
そしてこの見解をさらに押し進めていくと、その世界統合の最大の尖兵として浮かび上がってくるのが「帝国空軍」という恐るべき存在ではあるまいかと予想されるのである。 実のところ国際社会においては「情報制空権をもつ者が真実を作る」ということが唯一の真実である。そして日本に住むわれわれは、実はこの「帝国空軍」の空襲に毎日毎日さんざん痛めつけられて耐え難いダメージを受けているものと考えられる。それも高高度領域と低高度領域の両方からである。
まず高高度領域において情報制空権をもつ者はその気になれば、重要な国際問題の現場で自由に相手側に悪玉のレッテルを貼り、相手側の主張を空から粉砕することができるし、証拠のあやふやな大昔の事件を唐突に蒸し返して賠償金を要求したりすることもできる。
恐らく高高度において日本上空の情報制空権は米中側に握られているため、その絶対的情報制空権下では国家としてのまともな行動はほとんど不可能に近くなっている。現在そこまで厳しい空からの脅威に曝されている国は日本だけだが、一般的問題として、高高度領域で米中が手を組んだ帝国空軍の支配力というものはかくも強力で抵抗し難いものである。
一方低高度領域においては、メディアの無制限な商業主義などは「短期的願望の極大化」という面でまぎれもなく「帝国(無論それは必ずしも米国を意味するものではない)」に奉仕する存在である。それはある人々にとっては解放者だが、むしろ多くの人々にとっては退廃を強要する専制君主である。
ではここであらためて「帝国空軍」の定義をしておくと、要するにそれは
・「短期的願望の極大化」という主題に奉仕するメディアのエアパワーであり、世界各国の内部で発生してその画一性ゆえ世界中で手をつないでしまい、強大なパワーに膨れ上がる存在。
となる。これは世界統合を進める槍の穂先としての力において、資本主義経済の経済力よりも遥かに強力である。それゆえ仮想的ハートランドの真の戦略的意味なども、実はむしろそこに情報制空権の基地を確保することにあるのだとさえ言えるだろう。
準四次大戦では最も重要な戦いはどこで起こるか
では準四次大戦において、現時点で予測しうる最も重要な戦いはどこで起こるのだろうか。それは二つのものが予想される。
a 仮想的ハートランドでの「史上最大の無形化された戦車戦」
まず一つは、言うまでもなく仮想的ハートランドを巡る戦いであり、恐らくは米国の最大の戦略目的はここに「グレート・ウォール・ストリート」(万里の長城の英語名とのダブル・ミーニング)とでも言うべきものを建設することではないかと考えられる。実際それが完成した時に世界史は一つの終わりを迎える可能性が高い。
それを巡る戦略的な展開がどのようになるかはまだ不明だが、その過程でこの付近において「史上最大の無形化された戦車戦」が発生する可能性は高いと言える。
第二次大戦においては、ロシアの大平原において史上最大の戦車戦と言われる「クルスク大戦車戦」が起こったが、これはいわばその無形化された準四次大戦版であると言えるかもしれない。
将来の経済戦争において、中国の巨大市場と、そこを狙うライバルの多さを考えれば、その戦いの規模も容易に予想がつくというものであるが、ただし仮想的ハートランドを「確保」することの真の戦略目標は、そこに無形化された鉄道網と航空基地、つまり金融ネットワークと情報制空権の拠点を確保することにあるのだということには、あらためて注意を払う必要がある。
(ただしその「史上最大の無形化された戦車戦」が一体仮想的戦車何両分の激突に相当するものになるかの計算はいまだ予測の外にある。)
b 海側での「帝国空軍vs潜水艦」
第二の重要な戦いは、知的制海権を巡る海側のものであり、「帝国空軍」とそれに反抗する無形シーパワーによる、空と海の間の死闘が予想される。そしてこちらの方が、準四次大戦の本質をより浮き彫りにしている。なぜなら空と海の対決こそ、この無形化された大戦の本質だからである。
そしてシーパワー側が帝国空軍と戦おうとする場合、その戦術はどうしても潜水艦のそれに似てこざるを得ない。そしてこちらの方は一応の定量的予測が成り立つ。すなわち帝国空軍側は、航空兵力4000機分程度を投入して空から「海洋全体」を制圧しにかかるとみられるのに対し、勢力均衡側が潜水艦型の戦術パターンを中核に据えてそれへの抵抗を試みる場合、最低で250隻分の戦力が必要となろう。(実は「無形化世界・・・」の海軍力のオペレーションズ・リサーチの部分で行った計算は、実はこれを想定して行ったものである。)
これら二つが、恐らく準四次大戦における最も決定的な戦いになるものと予想される。(なお、日本の立場から見ると、前者よりも後者の方に、より本質的なプレーヤーとしての参加の余地がある。というより、それが日本のとれる唯一の戦略であろう。)
そして戦いを全体的な構図から見ると、それは世界統合側が内陸から仮想的ハートランドを確保し、そこを帝国空軍の本格的な根拠地として成長させて地球全体を制圧するのが早いか、それとも勢力均衡側が空からの攻撃を回避しつつ、海側からそれを包囲する体勢を作り上げるのが早いかの、壮大な世界史的競争という構図をとると予想されるのである。
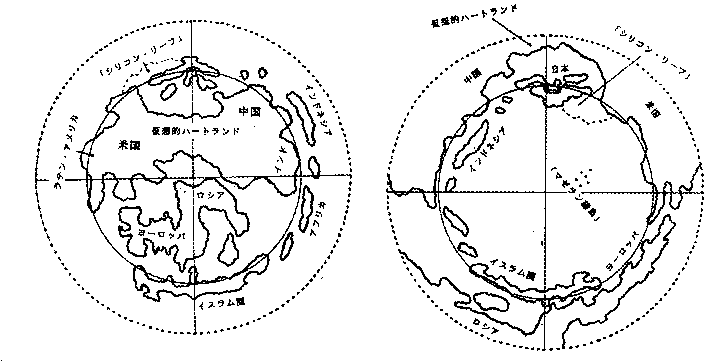 (図は無形化した戦略環境を仮想的な地形として球体に表現した「仮想地球儀」を二方向から見たもの。単に経済力を面積に換算しただけでなく、戦略的に重要な要素は仮想的に地形化してそれぞれ呼び名を与えてある。左図は「陸側」aの観点で見たものであり、右図はちょうどその反対方向からbの観点で見たものである。
(図は無形化した戦略環境を仮想的な地形として球体に表現した「仮想地球儀」を二方向から見たもの。単に経済力を面積に換算しただけでなく、戦略的に重要な要素は仮想的に地形化してそれぞれ呼び名を与えてある。左図は「陸側」aの観点で見たものであり、右図はちょうどその反対方向からbの観点で見たものである。
2.実際の経過(「初年度」前半)
・写真解説
当時のアジア経済の姿を仮想的陸軍力として可視化したもの。キャタピラ式の車両を用いずすべてタイヤ式であるという点で、日本経済の姿とは対照的である。当時は、新興国があっという間に機甲師団を編成できることから大いにもてはやされていたが、後に致命的弱点を暴露して壊滅した。
これが大変な威力をもつようになっていた理由を挙げると、まず第一にコンピューターによる射撃管制能力の飛躍的向上という要因があり、それは目標の座標をインプットしさえすれば、ボタン一つでそこに向けて正確迅速に投機資金の砲弾の集中豪雨を降らせることを可能としていた。(なお可視化の際の一つの決まりごととして、銀行は鉄道に、証券はトラックによる輸送機関にそれぞれ対応させることとする。)
今回の電撃戦の主役の一つであるIMF機甲戦力の主力。仮想的投入数を計算すると、タイ方面に800両、インドネシア方面に2000両、そして韓国方面へは4200両が投入されたことになる。本来は治安維持用の特殊車両であり、経済紛争地域へ高速で駆けつけ、障害物のコンクリート防御施設を破壊して進むという用途に適した形態だが、逆に言えば燃費が悪く短射程でおまけに車高が高いという、およそ戦車戦には不向きな設計であるため、まさか電撃戦の主役になろうとは事前には全く想像されていなかった。現在もなお多数がアジア諸国に駐留中。
マハティールの航空反撃戦
現在は、無形化時間をとって見た場合、準四次大戦「初年度」の後半にあるわけだが、とにかく初年度は米側の大攻勢と圧倒的勝利のうちに進展したと言える。この緒戦の大攻勢での圧倒的勝利によって、それまで没落する超大国と見られていた米国は、21世紀の主役として蘇生し、君臨する立場を一挙に取り戻すことができた。ではこれまでの経過について述べていこう。
準三次大戦の経過が、時間を1/10に縮小すると第一次大戦の戦略的経過に似ていたということからすると、今回もそれを第二次大戦初年度の経過と比較し、90年代の出来事を1939年のそれに重ねてみたいという誘惑にかられるものである。もっとも今回は両者が似てくるべき理由などは本来何もなく、また第二次大戦の場合「最初の1年」は39年9月から40年8月を意味するから、「年号」は半分ぐらいずれていることになる。
ところがそれにもかかわらず、偶然のいたずらによるものか、見方によってはかなり似た構図が浮かび上がってくるのである。それというのも第二次大戦の最初の1年間を見てみると、その経過は二つの突出した山場をもっていた。すなわちそれは、ポーランド電撃戦とフランス電撃戦の二つである。
それに対して準四次大戦の「初年度」つまり90年代における最大の事件(ただしまだ90年代は2年ほど残っているので断言はできないが)を戦略的重要度の観点から二つほどピックアップするとすれば、湾岸戦争と最近のアジア経済の壊滅の二つがそれに相当することには、ほぼ異論はないであろう。
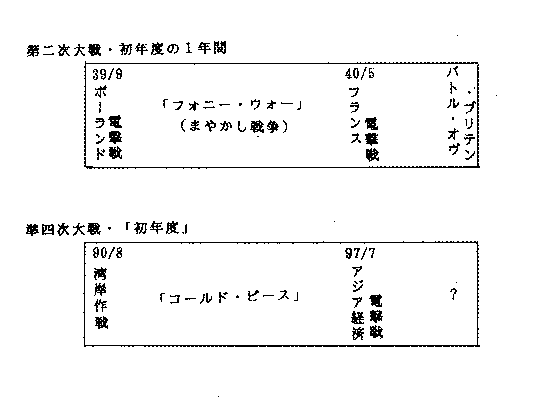 そして前者は純軍事的には「砂漠の電撃戦」と呼ばれ、もし数十年間の無形化された大戦争がこれから繰り広げられるとすれば、まさしくその開幕を飾るにふさわしいものだった。一方後者は純経済的なものではあったが、無形化戦略の観点からすると見ようによってはあたかも一種の電撃戦に似た構図が浮かび上がってくるのである。
そして前者は純軍事的には「砂漠の電撃戦」と呼ばれ、もし数十年間の無形化された大戦争がこれから繰り広げられるとすれば、まさしくその開幕を飾るにふさわしいものだった。一方後者は純経済的なものではあったが、無形化戦略の観点からすると見ようによってはあたかも一種の電撃戦に似た構図が浮かび上がってくるのである。
つまり意外なことに、「初年度」の山と谷は「偶数番号世界大戦」の間で偶然にも似た形になってきているのであり、何か世界史のジグソーパズルが思いもかけない形でつながって、違う色彩でかつてと同じ絵柄を描き始めているかのように見えなくもないのである。(その論理の延長でいけば、さしずめ現在の日本は「スピットファイアなきバトル・オブ・ブリテン」の時期にさしかかっているということになろうか。)
「初年度」全般の米側の戦力配備
もっともかつてのドイツの場合、もともとその国力は巨人とは言えず、おまけにその軍事力にしても、ヴェルサイユ条約の鉄格子の制約の中で作られた急ごしらえのものの奇襲効果にもっぱら依存せざるを得なかった。それに対して準四次大戦初年度の米国の大攻勢の場合もともと国力も圧倒的に大きく、有利な立場をバックに古代のローマ軍団よろしく自律的・連続的な行動をとることが可能となっている。
つまり今回の場合、奇襲的な電撃作戦とは別に、着実なスケジュールで進行する動きをその底流にもっていて、電撃戦の成果を活かしてそれらが前進し、その果実を確実に掌握するという形態になっており、むしろそちらの側に明らかな計画性が見て取れる(少なくとも電撃戦の部分に関しては、米側は計画性の存在を公式に認めていない)。
その部分はもう少し詳しく見てみると、主として3つのグループによる動きで成り立っていたと言える。識別のため、ここでは仮にそれをA軍集団、B軍集団、C軍集団と呼んでおこう。以下にそれを説明すると
・A軍集団とは、米国の軍事力を中心としたものであり、湾岸戦争で活躍したのは言うまでもなくこれである。(アメリカ陸軍、もしくはArmed ForceのAをとって命名。)
・B軍集団とは、中国との関係強化に動くための戦力であり、中国の市場を目指して進出した企業などもこれに含まれる。政府部門ではブッシュ政権がどちらかと言えばこれに熱心だったと考えられるため、頭文字のBをとって命名。これは今はやや小休止状態にも見えるが、90年代初頭においてはビジネス部門はかなり活発に動いていた。また現在の「中国超大国論」なども、これを支援する動きにある程度派生してできたものであることは間違いない。
B軍集団は、仮想的ハートランドの中心部へ直接向かうものであるため、ある意味では真の戦略的主力であると言える。
・C軍集団とは、インターネットなどの情報産業を中心としてアメリカの経済的覇権を確立しようという目的にしたがう勢力であり、クリントン政権がこれに熱心だったので、その頭文字のC(さらにコンピューターのC)をとって命名。特に政権内部において、ゴア副大統領のこれに関する指導力は際立っており、彼が「情報スーパーハイウェイ」の構想を政府のプランとして打ち出したことが、これを単なる経済面でのブーム以上のものにしたのである。なお前線指揮官という点では、「C軍集団」における最大の英雄がビル・ゲイツであったことは言うまでもない。
C軍集団は、A軍集団がその前進を停止した時期あたりから本格的に動き出した。
「初年度」前半の米国の大攻勢は、これら3つが主力となって複雑に絡み合い、相互に支援する形で動いていたと言える。いずれにせよこれだけの規模のものが3つ同時に動くとなれば、たとえ二つの電撃戦がなくとも相当な結果を挙げることになったはずである。勢力均衡側がこの打撃から立ち直って反撃できるかどうかはまだ明らかではないが、もしそれができなかった場合、この緒戦の大攻勢作戦こそが、準四次大戦の事実上の決着をつけた最大の出来事だったことになるだろう。
そしていささか皮肉なことに、米国は開戦時点ですでに第二次大戦とは完全に逆のパターンをとり始めていることになる。なぜなら第二次大戦の場合、最初米国は受け身の形で開戦して、緒戦からしばらくは守勢からの反撃の形をとったのに対し、準四次大戦では逆に米国が主導権をとって攻勢の形で開戦し、緒戦で大勝利を収めたからである。
準四次大戦の勃発とA軍集団の勝利−−湾岸戦争
では「開戦」の実際の状況を見てみよう。湾岸戦争こそ米A軍集団の晴れ舞台であったが、われわれの分析では基本的にこの湾岸戦争をもって「準四次世界大戦」勃発とする見方をとっている。
これは、ある歴史の見方からすれば単に一番目立つスペクタクルを無理矢理象徴としてそこへ持ってきたに過ぎないと見えるかもしれない。実際見方によってはそれは単なる地域紛争の幕開けでしかなく、たとえその背後の石油の支配権を巡る問題に注目したところで、歴史の流れに位置付けにくい空虚なショーでしかない。
しかしながら、もし米国を中心とする「世界統合化」こそが準四次大戦の主題であるという見方をとった場合には、この「砂漠の電撃戦」は単なる象徴以上の大きな現実的・歴史的意味をもってくる。すなわちそれは、米国がもはや世界唯一の超大国となったことを疑問の余地なく高らかに宣言した事件だったからである。
実のところあの事件においてもたらされた最も大きな影響は何だったかといえば、それは旧ソ連製の兵器によって構成される軍事力が、米国の軍事力の前にはどれほど太刀打ちできない弱いものであるかを、全世界に向かって疑問の余地なく実証してみせたことである。
これは軍事作戦としては空虚なスペクタクルだったかもしれないが、むしろ無形化領域においてその圧倒的なデモンストレーション効果は歴史にとって大変な影響を与えたはずである。実際あの後、米国の軍事力に対する疑問の声はぴたりと止んだ。これによって、物理的・軍事的枠組みの基本ラインと、その上空の情報制空権ががっちり確保されたのである。
無論現在見られる米国の復権がこのA軍集団一つの動きで成ったわけではなく、他の二つと組み合わされることでそれが成ったのだが、その貢献が極めて大きかったことは確かである。
なお、国連を使って米国の軍事力を存分に使うという試みは湾岸戦争以降も続けられた。そしてそれはソマリアのPKO「希望回復作戦」−−92年末のこの作戦のスタートは、上陸予定地に兵士より大勢の報道陣が待ち構え、迷彩服を着た決死の表情の海兵隊員が混雑するカメラマンを掻き分けながら上陸するという、前代未聞の上陸作戦となった。−−の挫折によって、一応その試みはそれ以上進めることが限界であると確認された。
つまりソマリアにおいてA軍集団は一応終着点に達し、緒戦におけるA軍集団の前進はそこで停止したと言える。
準四次大戦の開戦宣言
そして湾岸戦争の開始とともにブッシュ大統領によってなされた「新世界秩序」演説(91年1月29日)は、当時はそれほど意味深いものには見えなかったが、今にして思うと一種の開始宣言としての象徴的な意味をもっていたと言える。それを宣戦布告とまで呼ぶのは少々問題があるかもしれないが、少なくともそれは今後の世界では世界唯一の超大国である米国を中心として形成される秩序が「世界秩序」であることを米国政府が公式に宣言したものであることは、何としても否みがたい。これもまた、世界統合と勢力均衡の死闘が準四次大戦のテーマであるという見方をとった場合にのみ、開戦宣言としての意味をもつのである。
なお、開戦の日時を90年8月のイラク軍クゥエート侵攻および「砂漠の盾」作戦開始時とするか、それとも5か月後(無形化時間では16日後)の91年1月の多国籍軍の「砂漠の嵐」作戦開始の時とするかは、まだはっきりしていない。
注)開戦の謎−−米国にとって湾岸戦争は本当に受け身だったのか
なお開戦の日時をどちらに置くかという問題は、「開戦意図」の解釈について論じることを要求するため、次の憶測についても言及することが一応必要になるようである。
それは、公式にはこの一連の湾岸戦争は、フセインのクゥエート侵攻によって発生したものであり、米国は一応受け身の形で開戦した形になっているが、それが本当に「受け身」だったのかについて疑問符をつける向きがあるということである。
それによれば米国は、冷戦終結後の唯一の超大国としての地位を確立するため、それをどこかでデモンストレーションしたいと願っており、イラクが問題を起こせばむしろそのチャンスが生まれると捉えていた。
それゆえイラクの軍事力を劇的に破壊するため、それを空軍力によって撃滅できる絶好の場所に誘い出したいという意図が当初から米側に存在し、そのためグラスピー駐イラク大使に命じて「米国はクゥエート問題に介入しない」との誤解を与えるようなシグナルを故意にフセインに送り、フセインはそれにはめられてクゥエート侵攻に出てきてしまった、つまり湾岸戦争はその発端からしてすでに米側のシナリオによるものだったのではないかというのである。
この種の話はとかく「陰謀の過度の邪推」に陥りやすいものだが、しかし状況証拠がそれなりに多いことも事実である。まず、その前哨戦というべき89年のパナマ侵攻作戦を鮮やかに成功させたことで、米国は軍事力の積極的な使用に自信を深めており、もっと大規模な舞台を求める動機は十分に存在していた。(おまけにこのパナマ侵攻作戦が、悪の麻薬王ノリエガ将軍追放という表向きの理由の裏で、実はパナマ運河の管理権を奪取するための純然たる侵略だったという衝撃的なドキュメンタリーが、BBCかどこかで作られたことがある。ただし湾岸戦争の場合、すでに悪の代名詞となっているフセインを擁護するような番組は多分もう作れないだろうが。)
第二に、イラク軍の侵攻意図は事前に衛星写真によって米側には明白にわかっており、それに基づいて米国が一言フセインに警告を行えばそれだけでクェート侵攻を阻止できたはずなのに、侵攻意図ありとの情報分析報告はなぜかホワイトハウスには無視され、イラクへの警告も行われなかった。
第三に、それほどの見込違いをしていたにもかかわらず、侵攻が起こった後の米側の対応はまるで準備でもしていたように迅速に行われ、実に兵力50万を派遣する「砂漠の盾」作戦がたった数日以内に開始された。一般に米国の動員の迅速さは定評があるが、それにしてもこれを過去の、明らかに見込違いで戦争に突入してしまった朝鮮戦争の時と比べると、やはり異常にスムーズである。(それに朝鮮戦争が結局は骨折り損のくたびれ儲けだったのに比べると、湾岸戦争はほとんど無視できるほどの損害で信じ難いほど大量のものを獲得することに成功しており、動機の点では十分以上のものがある。)
さらに「司令官たち」(ボブ・ウッドワード著)によると、ブッシュ大統領が事態発生からわずか3日後に発表した声明ですでに、湾岸への米軍の派遣が、単に事態のこれ以上の拡大を防ぐ消極的安全策や威嚇ではなく、積極的に戦闘を行ってイラクの軍事力を撃破することを目的とすることが明白に宣言されていた。
要するにこの時すでに決定的な決断−−つまりベトナムでの挫折以後初めて、米国の青年たちを大規模に砲火の中に投げ込むという歴史的決定−−がなされていたのである。しかもパウエル統合参謀本部議長はその重要な意志決定に際して何一つ相談を受けておらず、演説を聞いて驚いたという。それらはいずれも、政権内部の一握りのグループが事前にかなりの確信をもってシナリオを準備していたと邪推するに十分なものである。
もっともたとえそうだったとしても、当時米側には恐らく陰謀という意識は乏しく、ちょうどローマが「パックス・ローマ」の理念に基づいて軍隊を発進させるとき、通常の国家にあてはまる概念は自らには適用されないと確信していたのに似た意識がそこにあったのだろう。
そしてそれが受け身だったのか故意だったのかについての決定的な証拠が世に出ることは恐らくなく、将来も「準四次大戦開戦の謎」という形で、よくある歴史の謎の一つとしてくすぶり続けることになるのではあるまいか。
「フォニー・ウォー(まやかし戦争)」の期間と追い詰められる日本
湾岸戦争の硝煙が収まった後、世界はしばらくの間、流れがどこへ向かっているのかよくわからない時期を経験する。ちょうどそれは、第二次大戦の勃発後、ポーランド戦が一段落した後に間もなく、不活発でめりはりのはっきりしない「フォニー・ウォー(まやかし戦争)」と呼ばれる期間がしばらく続いていたことを、どことなく連想させる。
実際この時期には世界の状況は苦しまぎれに「コールド・ピース」などいろいろな言葉で呼ばれ、将来の世界問題は「地域紛争の時代とその対応」が主題になるなどと言われていた。そして米国はたとえ湾岸戦争に勝利を収めたといっても、経済をはじめとする無形化領域では衰退からの復活など夢物語と見られており、その後の無形化領域での大勝利など想像もされていなかった。
一方この時期に無形化領域で最大の有力プレーヤーと見られていたのはアジアNIES諸国である。そこは当時「世界唯一の成長センター」の名をほしいままにしており、アジア経済こそ未来のスターだというのが大多数の専門家の見解だった。そしてこのあたりから、準四次大戦は本格的に無形化の様相を呈し、戦略の主軸はもっぱら無形化領域に入り込んでいく。
さてアジアNIES諸国の経済を仮想的陸軍力として見た場合、それは日本側とは一見しただけでもわかる大きな違いがあった。
日本側のドクトリンは機械化歩兵−−中小企業−−を主体とする戦法をとるため、それを可視化した場合必然的に装軌式APCが多くなる、つまり大部分の車両がキャタピラ化された形態になるのに対し、アジア諸国の場合はこれとは対照的に、恐らく大部分の車両がタイヤだけで動く装輪式車両の形態として可視化されることになる。
実は興味深いことに、経済部門ばかりでなく物理的な軍事部門でも、当時こうした装輪式車両は兵器見本市で大人気を博していた。すなわちキャタピラのかわりに大型のタイヤを6〜8個装備し、軽戦車並みの砲および砲塔を搭載して、火力に関する限りは戦車にそう劣らないという車両が、軍隊の新装備の趨勢として流行していたのである。
これが人気を集めていた理由をいくつか挙げると、まずこのようなタイヤで動く車両は、キャタピラ式に比べて安価・軽量で、操縦に訓練をあまり要しない。欠点としては不整地行動能力が低いことだが、逆に道路上では高速発揮も可能だし他の走行性能もキャタピラ式より格段に高い。
つまりこれを導入して主力とすれば、かなり容易に一種の代用戦車を手に入れて高速で前線へ送り出せることになり、あまり贅沢な装備を買えない国にとっては魅力的に映るのは当然であろう。
そしてこの一般的特性は経済戦争の場合にもかなりの程度共通しており、特に当時のアジア経済の立場には極めて適したものだったのである。本来ならばこのような代用装備は最前線では限定的にしか使えないはずだが、当時のアジア経済のようにひたすら後ろから追い上げをやっているような場合、日本や米国が前線まで進出しているところでは、その後方ではブルドーザーの通過後のように道路が形成されていることが多く、また路外についてもどこが車輪でも通れてどこが通れないかの地図が大体できている。
そのためその道路からあまり離れずに最前線の少し後ろで限定的な戦闘を行う限り、戦車並みの火力を備えてあっという間に前線近くまで進出できるわけであり、それは今までの低開発国がいきなり最先端の工業を保有できることを意味する。
また一方それを支援する機械化歩兵−−中小企業に相当−−に関してはアジア諸国はまだ未熟であり、兵員の輸送はAPCでなく通常のトラックを用いて行う形になるから、結局可視化するとほとんどの車両がタイヤで動いている構図になるという寸法である。

ともあれこの特性に魅力を感じたアジア諸国はこぞってこの流行の新装備を大規模に採り入れ、きのうまで歩兵しかもっていなかったような国々が突然近代化された経済的機甲師団を前線に忽然と出現させたさまを見て、人々は驚いた。
一方これとは対照的に、日本は緒戦から受け身に回って一方的に敗北を喫し続けていたため、まるでアジア諸国に背後から追い上げを食う形となって、その明暗は際立って見えた。しかしながら、このアジア側の新装備は間もなく致命的な欠陥を露呈することになるのである。
NIES経済電撃戦
帝国側の電撃戦とアジア陸軍の壊滅
さて準四次大戦の開始以来、最新鋭の装備に身を固めて快進撃を続けていたかに見えたアジア諸国の経済は、97年に入って突如鉄槌を下されたような壊滅的敗北を喫し、経済的国土の大半を喪失した。実のところ事態の全貌とその意味が判明するにはまだしばらく時間がかかるかもしれない。なぜなら、ひょっとしたらこれは準四次大戦全体を見ても指折りの「電撃戦」としての意味をもった出来事であったかもしれないからである。そして現在まだそれは完全に終息してはおらず、それゆえ以下には、現在判明していることだけをとりあえず記すことにする。
開戦前に整備されていた新兵器
この電撃戦は、準四次大戦初期における無形化された地上軍の新兵器が何であるかを明らかにしたという点でも特筆すべきものだった。つまり仮想的な陸軍力として見た場合、この事件は歩兵や野戦軍の力にほとんど出番がなかったという点に最大の特徴があったのである。しかしそれならば機甲戦がその主体だったかと言えば、それもまた真実ではない。むしろ強いて言えば、列車砲の砲撃戦がこの戦いの最大の主役だったと言えるだろう。
つまり世界中に張り巡らされた金融の鉄道網の上を高速で移動し、目標へ自由に投機資金を浴びせかけるという、いわば「仮想的列車砲」とでも言うべきものが登場しており、それはこのときすでに戦車の破壊力さえ上回る力を得るに至っていたのである。
 今回アジア経済を壊滅させた最大の主役の可視化。写真のものは口径30センチ級以上、1発当たり500万ドル相当の為替投機資金を、標的とされた国に叩き込む能力をもつ列車砲の姿である。推定総重量260トンの怪物であるが、今回参加したものの中ではこれでも中型に属し、恐らくジョージ・ソロス直属の列車砲はこれより遥かに大型だと考えられる。アジアが一段落した後はむしろ標的を日本に向けて、連日火を吐き続けている。
今回アジア経済を壊滅させた最大の主役の可視化。写真のものは口径30センチ級以上、1発当たり500万ドル相当の為替投機資金を、標的とされた国に叩き込む能力をもつ列車砲の姿である。推定総重量260トンの怪物であるが、今回参加したものの中ではこれでも中型に属し、恐らくジョージ・ソロス直属の列車砲はこれより遥かに大型だと考えられる。アジアが一段落した後はむしろ標的を日本に向けて、連日火を吐き続けている。
またその威力をさらに倍加する要因として、投資情報を支配するいわゆる「格付け機関」が空中に常駐していたことも大きい。これを可視化するとすれば、さしずめスマート砲弾を空中から誘導するための「イルミネーター機」と考えるのが適当であろう。
つまりこのイルミネーター機が高高度を旋回し、それが搭載するイルミネーターで目標を照射すると、列車砲・自走砲などから適当に空に打ち上げられていたスマート砲弾(弾頭にレーザー・シーカーをとりつけた砲弾)のシーカーがそれを捉えて弾道をそちらに向け、照射目標に一斉に落下していくのである。
これらはいずれも移動目標に対しては本来効果が薄いが、座標がわかっている道路や線路に貼り付いている目標に対しては絶大な威力があり、今回の状況下でこれは突然花形兵器となった。
さらに言えば、こうしたことは実は背後にもっと大きな要因があって起こったことであり、それは開戦前に陸上で一種の「補給革命」と呼ぶべきものが起こっていたためである。
従来の経済戦争においては、金融機関はその補給線を構成していた以上、必要欠くべからざるものではあったが、あくまでも戦いの決着をつけるのは前線の野戦軍同士の交戦だった。しかしながら「量的変化が質的変化を引き起こす」の言葉どおり、鉄道網が余りにも発達した結果、ついに主導権は逆転し、補給線の攻防がすべてを決する「補給革命」が経済の世界に起こったのである。
そしてまたそれまで一種の島国状態にあって鉄道やトラックの乗り入れができなかった国といえども、沖合に「オフショア・ポイント」すなわち国際的な交通集結地点が作られてそこが発達することにより、国土全体が知らない間にすっぽりそれらの射程に収まっていた。
ともあれ鉄道網の極度の発展は、補給のための貨車にも、砲撃地点を探す列車砲にも飛躍的な機動力を与え、これによって鉄道の力は野戦軍の力より戦術的に上回ることとなった。要するに準四次大戦開戦前の時点で、すでにこれらの新兵器が待機の状態にあり、威力発揮の舞台を求めていたのである。
そして今回の電撃戦を代表する存在として名を世界に知られた人物は、「史上最強の投機家」と呼ばれたジョージ・ソロスであり、今回の事件自体が多分に彼の名によって象徴されている。(しかしながら、その配下の砲兵集団を米国の軍集団として分類することは控えておきたい。なぜならそれは以前に述べた区分にしたがえば「米国防軍」の戦力であるというよりはどちらかと言えば「帝国直属」と言ったほうが正確だからであり、ソロスの所属もさしずめ帝国の砲兵師団の指揮官といったところだろうか。)
アジア陸軍の脆弱性
さてこのような新兵器が使用されるとなれば、アジア側の装備には致命的な弱点があることがわかる。なぜなら基本的に先ほど述べたような、路上しか通れない防御力の低い装輪式車両が、前線までの道路上に塊になって列を作っている仮想的状態というものを考えると、それは砲兵たちにとって格好の目標に他ならないからである。
これに比べると日本型、すなわち全部がキャタピラを履いている形態の場合、もともと車両は道路から外れて行動していることが多いし、また砲撃が始まっても、ほとんどの車両がキャタピラを活かして急いで路外に分散してしまうので、直接的には即座に壊滅することはない。ところがアジア陸軍の場合には道路から外へ出ることができず、また砲兵側はすでに道路の座標を射撃統制装置にインプットしてあるため、道路上にアヒルのように動けずにいる車両を残らず狙い撃ちできることになる。
また、このようにキャタピラ式でないにもかかわらず砲だけは一人前のものを搭載しようとして無理をした車両の場合、軽量化のため余剰重量を極限まで削らねばならないはずだから、単独での防御力が低い。つまり戦闘力自体が外からの補給に過度に依存する傾向がある上、いつも早い速度で動き続けていなければ、弱点を露呈しやすいのである。
これはある種のジレンマであろう。つまり路上を高速で移動できることが唯一の強みであるにもかかわらず、すぐに次の補給が必要になってしまうというのだから、補給部隊も高速で追随できねばならず、結局高速で走れるトラックをかなりの台数用意し、常にそれらをすぐ後ろに従えていなければならない道理である。
それゆえそれが威力を発揮するためには、広い面積の機動の余地を確保し、なおかつその全域にわたって補給が可能でなければならない。そして多くのアジア諸国の場合、それを可能としていたのは、自国通貨が比較的高い状態に維持されてそれだけの仮想面積を確保できていたからである。また当然、必要とされる大量の補給用トラックは自国では調達は無理で外国から借りねばならず、そしてその保護には情報制空権が不可欠である。
こういう脆弱な状態というものは、どこか一個所が切断されると戦線全体が崩壊するという点で、それ自体が砲撃にかなり弱い状態であり、快調に進撃を続けていたかに見えたアジア側は、二重の意味での脆弱性を抱えていたことになる。
そして彼らは直前までそんな危機が襲いかかることに対する備えなどほとんどしておらず、前線にばかり目を奪われて、横腹を砲撃でやられるとは想像していなかったのである。そしてひとたび奇襲を受けるや、その壊滅の深刻さは日本などの比ではなかった。
電撃戦の開始
97年の7月、砲撃の嵐と共に電撃戦は始まった。口火を切った列車砲の巨弾が最初の標的に選んだのはタイ経済の通貨バーツであり、そこへ集中豪雨のように砲弾の雨が降り注いだのである。そしてまた高高度を旋回するイルミネーター機からの照射光が、次々に死の宣告のように地上を襲い、スマート砲弾を逃げ惑う者たちの頭上に誘導していった。
そして目標とされた側は前記のような脆弱性ゆえ、単に通貨が暴落したに留まらず、路上で身動きのとれなくなった車両は次々炎上して師団ごと壊滅、タイ経済はトランプの家のように吹き飛んでしまった。
このドミノ倒しの中、帝国の砲兵軍団の列車砲は次から次へと砲撃目標を転換して、その砲身から火を吐き続け、続いてインドネシア・マレーシアなどにその巨弾が唸りを上げて落下し、それらの国々を片っ端から雪崩のような壊走に巻き込んでいった。
 ・写真解説
・写真解説
電撃戦の火蓋を切る国際投機筋の仮想的列車砲。最初の目標はタイのバーツであり、この砲撃でタイは阿鼻叫喚の巷と化した。
そしてこの電撃戦の戦術は、すぐに引き続いて第二段階に移行する。つまりこの集中的な準備砲撃で陸上兵力を壊滅させた後、無抵抗に近い戦場を前進して重要拠点を占拠するというのが、この戦法の最終段階なのである。
その際占拠すべき戦略目標は主として次の2つである。まず第一は、IMFを表に立てて相手国の経済政策の中枢を押さえることである。一般に、通貨が砲撃で壊滅して暴落してしまうと、対外的な支払いができなくなるため、IMFから緊急融資を受けねばならない。ところがIMFは、融資を行う代償にその国の経済運営に介入する権利をもっている。つまりIMFの緊急融資を要請することは、経済政策において主権を喪失するに等しいのであり、そしてIMFの主導権は米国が握っているのである。
極端な言い方をすれば、もし一般に現代の国家の「首都」が政治的首都と経済的首都の二つに分かれて(ちょうどワシントンとニューヨークの関係のように)存在しているとすれば、IMFの進駐は後者の経済的首都を一時的に占領するに等しいのである。
第二の戦略目標は、情報制空権の拠点を陥落させること、つまり「世界最強の成長センター・ASEAN」というステレオタイプの破壊である。実際、その空の拠点あればこそ、その情報制空権の傘の下で投資も集め、通貨価値を高く保っておくこともできたのである。
そしてこのステレオタイプの破壊は、同時に「日本型システム」の正当性を否定することでもある。実はアジア諸国の経済は、機械化歩兵を主力としていなかったという点で日本型システムとは似て非なるものだったのだが、米側にとってはむしろそんなことは無視するのが当然だったろう。
この空の拠点は、米国にとっては目ざわりなものであり、実際かつての米国経済の凋落のイメージは、飛躍的に発展するアジア経済の力のそれと常に表裏一体で語られていた。そこでそれを潰してしまえば、米国経済磐石論をイメージの点で強化することができ、事実その拠点が無力化された後には、投資先として米国以外頭に思い浮かばないほどである。
そしてIMFの進駐によってASEAN諸国の経済政策の独立を奪っておくことは、恐らく将来の中国での作戦に備えて、その側面の安全を確保しておく狙いがあると思われる。
あっけなく潰えたタイの抵抗
では電撃戦の詳細を見てみよう。最初に標的とされたタイでは、降り注ぐ巨弾の嵐の中、政府はバーツ防衛のため帝国の列車砲群へ向けて対抗砲撃を大規模に開始した。
だが帝国側の砲撃の凄まじさたるや、到底そんなもので押し返せる規模ではなかった。それでもタイ政府はこの一戦にすべてを賭ける覚悟で介入資金としての外貨をかき集め、その貴重な弾薬を残らずバーツ死守のためのその対抗砲撃作戦に投入していった。
その際投入された砲弾の量は28cm級砲のエネルギーへの換算で優に1万発分(=300億ドル)を超えたが、焼け石に水でほとんど効果も上げないままみるみるうちに底をついていった。
そして前線はこの危機的状況に敏感に反応し、アジア諸国が本来内部に抱えていた脆弱性が突如現実のものとなる。まず後方が崩れ始め、補給縦列が撤退を始めた。
本来こうした補給線を構成する金融機関は、古典的な「健全経済」の場合、基本的に自国が保有する鉄道やトラックで構成されるのだが、タイの場合にはそれはもっぱら外国に依存していた。つまり彼らはもともと単なる契約外人のトラック運転手たちのようなもの、というよりむしろ現在攻撃を加えている帝国軍こそが彼らの親玉と言ってもよく、タイとの結びつきは傭兵以下だった。
そして彼らはみな、空を舞うイルミネーター機の照射光がどこを指しているかを見るための装備をもっており、その照射光が空からサーチライトのようにタイ全土を照らしているのを認めた。それが死を運ぶ予兆であることを知る彼らは、直ちに前線のタイ陸軍と縁を切って、一斉に国外へ脱出を始める。
もしこの時期のタイの状況を可視化するならば、恐らくそれはトラックの大集団が帝国側の管制のもとフルスピードで一斉に国外に脱出していく物凄い光景となるはずで、タイ国内の道路という道路が見渡す限り突進するトラックの濁流と化し、その轟音が砲撃の雷鳴や地響きと重なって、あたかもタイ全土が鳴動しているように見えたことだろう。
一方逆に、補給部隊に見捨てられた前線の機甲部隊の側は一夜にして戦闘能力を失うことになる。それらは道路に縛り付けられて完全に身動きがとれないまま補給も退路も断たれてしまい、自力での防御戦闘能力がないに等しいため、ただ路上に座り込んだアヒルのように、一方的に射的の目標とされて全滅を待つばかりとなってしまった。
また唯一の希望だった政府側の対抗砲撃作戦も、瞬く間に弾薬が尽きて津波に押し流されるように終息していく。そして国全体から補給物資ごとトラックの大群が逃げ去ってしまっている以上、その残弾を撃ち尽くした時点でもはやタイ国内には有効な反撃のための兵器も弾薬もほとんど残っておらず、電撃戦の前進に対してほとんど丸腰の状態となったのである。一方このころ米側の戦線の後方では、作戦開始以来戦線の背後で待機していたIMFの地上部隊が、出撃準備のため次々とエンジンをかけ始めていた。(ただし、その表向きの名称はあくまで「救援軍」であったが。)
そして8月、無形化時間で「D+4〜5日」(つまり作戦開始からたった「4〜5日」後)の時点でタイは早くも抵抗能力をほぼ完全に喪失し、いよいよIMFを先頭に立てた地上侵攻部隊がタイの経済的首都に突進を開始する。
地上戦第一陣の規模は、IMF主力の仮想的戦車800両、支援車両2600両という量であり、これがどの程度の規模かを過去の軍事作戦と比較すると(規模比較の場合、運動量法則によってこれを1/10にするというルールがあるため)、第一陣は主力80両を含む合計340両を動員する作戦規模と同等であり、これはせいぜい機甲1個師団程度を投入する作戦規模の感覚で捉えるべきものである。
しかしそれでも、砲撃で根こそぎにされた戦場にはその快速の前進を阻むものは何もなく、あたかも無人の地を行くが如き進撃だった。そしてほとんど無抵抗のままタイの経済的首都はあっけなく陥落する(D+5日)。これはこの電撃戦での最初の首都占領であったが、怒涛のような電撃戦にとっては単なる通過点に過ぎず、主力はそれを越えてさらに前進していった。

一方作戦開始の時点で、もう一方の戦略主目標である航空拠点もまた熾烈な攻撃にされされていた。アジア各国の前線付近にある「世界最大の成長センター=アジア」というステレオタイプの拠点は、もしそれが維持され続けるならば、砲撃を加えてくる帝国側の列車砲に逆に空襲を加えて押し返すことも可能ではあったろう。
しかし電撃戦の口火を切った準備砲撃の一部はまさにここに照準を定めていた。作戦開始と同時にこれら前線航空拠点にも巨弾が降り注いで滑走路上で炸裂、ほとんど1機も離陸できないままこれらの航空拠点は壊滅し、アジア側は作戦開始とほとんど同時に情報制空権を完全に失った。
この非常事態においてマレーシアでは、それでもその情報制空権を失った空にマハティール首相自身が舞い上がり、直接空から航空作戦を指揮して、ソロス率いる帝国の砲兵師団に何とか一矢を報いようとする。
その様子はさながらマレーシアのみが空中指揮機から指揮されて反撃を行なっていたかのように見えなくもないが、しかしマハティール側には、遥か高高度をコンドルのように悠々と舞うイルミネーター機を墜とす手段がないうえ、彼が航空攻撃を加えるたびに、帝国側はまるで人質にでもとっているように射程内のマレーシア経済に報復砲撃を加え、ついには報復を恐れて国内から航空作戦の中止を求める声が上がってくる有様だった。
結局マハティールの果敢な反撃もさほどの効果を上げなかったが、それでもマレーシアの地上の状況はもともと他のアジア諸国に比べるとさほど脆弱ではなかったため、辛うじて経済首都陥落の事態は免れた。
ところがそれに比べるとインドネシアの状況は遥かに壊滅的だった。インドネシアの通貨ルピアは他のどれよりも激しい砲撃にさらされ、一挙にそれは1/4にまで下落し、国民経済全体がその狭い領域に押し込められて呻吟させられることとなった。
それでもスハルト大統領は陥落寸前の首都前面で絶望的な抵抗を試みたが、結局は降服し、IMFのカムドシュ専務理事が腕組みして見守る中を降服文書に署名させられるという、屈辱的な光景が世界に伝えられた。
かつてと似てきた電撃戦の戦略的構図
これまでの経過を見ても、その戦略的構図が1940年のフランス電撃戦に様々な点で似てきてしまっていることがわかる。
かつてのフランス電撃戦の場合(一般には誤解がなかなか解けないようだが)、ドイツの勝利は必ずしも戦車の鉄の力を正面から遮二無二ぶつけることでもたらされたものではない。むしろ事前の予想ではドイツの機甲戦力は質、量ともにそれほど大したものではないと見られており(事実ハードウェアに関してはそうだった)、むしろ戦略的に戦線の「後方を突いた」ことがその決定的要因となっていた。
つまりフランス軍側は戦線の北寄りのベルギー方面が主戦場であると思い込んでおり、そこにほとんど全軍を集中させていた。ところがドイツ側の戦略はその裏をかき、むしろもっと南方に機甲部隊を集中的に配備して戦線に穴を開け、その突破口から機甲部隊が連合国側の背後に雪崩れ込むというものだった。
そのためフランス軍はほとんど戦っていないうちに、いつの間にか後方の広い領域をドイツ戦車の大集団に蹂躙されており、逆にドイツ戦車の多くはほとんど一発の弾丸も発射せず無人の地をひたすらキャタピラだけを動かして突進しているという有様だったのである。(もしまともに正面からの戦車戦となった場合、ドイツは前進の途上で大きな損害を出してあのような迅速な勝利は難しかったことだろう。)
こうしてみると、今回の無形化された電撃戦も見方によってはややそれに似た構図をもっていることがわかる。まず第一に、アジア諸国は従来の常識からする「前線」こそが主戦場と見なし、低コストを活かして生産・輸出能力をじりじり競っていくという在来型の経済戦争を考えていた。
そのため戦線はやや危険なまでに前方に出過ぎており、横腹や後方はかなり無防備に放置されていた。それに対して今回の電撃戦はむしろその背後の領域に広がる「通貨の過大評価による仮想的面積」を狙ってそこを崩壊させるという点で、かつてのフランスと同様の弱点を突かれた格好になっていたわけである。
アジア側としては、在来型の経済戦争ならば十分勝ち目がある、あるいは負けるにしても少なくともそれは長時間をかけて後退していく形になるはずだと考えていたことは間違いなく、それゆえこのように背後を突く戦略は完全に彼らの虚を突く格好になったわけである。
さらに細部の戦術を見ても、第二次大戦のドイツの初期の電撃戦の戦術形態が「急降下爆撃機が耕し、戦車が前進する」と評されており、耕された後の地表を進む戦車は、ほとんど交戦らしい交戦もせずに前進することが多かった。そしてこのことに対応させると、今回はさしずめ「イルミネーター機の誘導砲撃で耕し、IMFの地上部隊が前進する」パターンになっていたと言えるだろう。実際IMFはただ無人の領域を突進するだけが取り柄の戦力なのだから、このようなパターンの元ではじめて有効な戦力となり得たのである。
ともあれこうした要因による奇襲効果が余りに際立っていたため、本来なら何年もかかるような経済勢力地図の塗り替えがあっという間に劇的に起こるという、それまで想像もできなかったことがはじめて可能となったわけである。(そういったことを考えると、一部で言われているような「財界と政界のなれ合い体質というアジア的特性」などはおよそ戦略的本質からは程遠い要因であることがわかる。)
二つの戦争を比較して、時期を同じくして似たような一種の電撃戦が発生してしまったこと自体は恐らく偶然によるものである。ただ、予想もしないほど急速に勢力地図が塗り替えられてしまったことは、明らかに戦術的パターンの共通性という同一の原因による分析を許すようである。
電撃戦のクライマックス−−韓国の壊滅
そして「D+9日」、物理的時間では10月ごろ、怒涛のような電撃戦の先頭はいよいよ韓国を襲う。そしてその壊滅の急速だったことは歴史にも稀なほどであり、つい最近まで経済大国の仲間入りをしようかと言っていた自信満々の有力経済国が、あっという間に経済破局に陥ってしまった様を見て、世界は驚愕した。
韓国は予想もしなかった戦線崩壊にパニック状態となり、国内では外貨危機の助けとするため国民に対し、家の引き出しに眠っている外貨やコイン、あるいは貴金属などを供出して、国家の危機を乗り切る呼び掛けがなされた。
しかし雪崩のような壊走は国民の供出運動などで乗り切れる事態ではなく、12月には早くも韓国は壊滅状態に陥って、「D+14日」、この電撃戦の最大の中核戦力が経済的首都への突進を開始する。その仮想的規模は機甲戦力換算で、IMFの主力が4100両、支援車両7200両という、IMF史上最大と言われる巨大な規模のものだった。
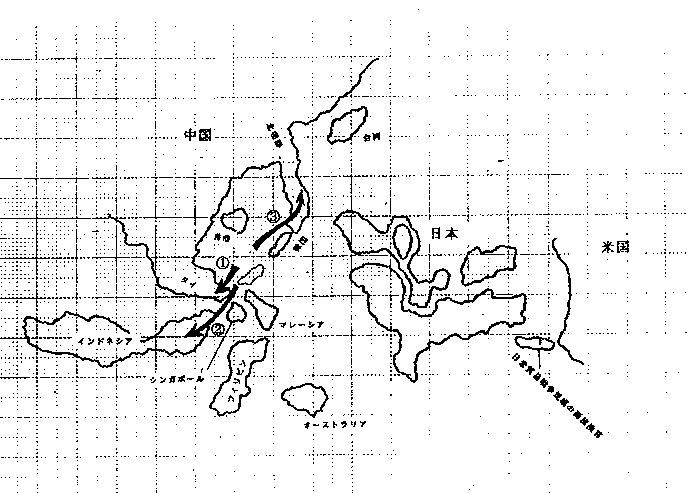 ・図の解説
・図の解説
「仮想地球儀」上での電撃戦の進展の様子を示す。今回のNIES電撃戦はまず(1)タイ方面、次に(2)インドネシア方面、そして(3)韓国方面へと進んでいった。
そして単に規模の点のみならず、戦略的意味の点でもこれがこの電撃戦の最大の目的だったと一部で言われている。無論米側は謀議の存在を否定してこれは完全に自然発生的なものだと主張し、そうした見解を嘲笑しているが、韓国側では少なからぬ人々がこれを計画的なものだと考えており、両者の主張は並行線をたどっている。
しかしともかく動機の点では少なくともそれは十分すぎるほどの戦略的意味をもっていた。それというのも、韓国経済はそれまで日本以上に閉鎖的で、外資の侵入を頑なに拒む体制をとっており、その堅固なことはあたかも国土全体に政府のコンクリート防御施設が張り巡らされたようなものだったからである。
それまで米国は戦線正面からそれをこじ開けようと努力を繰り返していたが、韓国側のマジノ線のような頑強さにさんざん手を焼いていた。ところがIMFが戦線背後から雪崩れ込むことができれば、その十重二十重の防御施設を後ろから回り込んであっさり破壊することができることになるのである。
本来なら韓国は、自側がそのような弱点をもっていることを認識して、十分な防衛手段を講じておくべきだったろう。しかし今回はその戦略は余りにも奇襲性が強く、従来の戦略常識の裏をかくものだった。
実際IMFがそこまでの決定的な戦略的役割を果たすことになるなどとは事前に全く想像もされておらず、言ってみればそれは主力「武器」というよりもむしろ後方で治安維持に当たる一種の火消し用の支援車両のようなものだと見なされていたのである。
ところが投機資金の嵐のような砲撃で国全体が麻痺状態に陥るという予想外の状況下では、その特性は絶妙な戦略的適合性と奇襲性を帯びることとなり、韓国はその前進を阻止する手段を全くもっていなかった。
実際に事態がかなり危機的状況へ進みつつある時期においてさえ、韓国ではかなりの人々がそれに気づかず楽観視していたという有様で、このあたりもどことなくかつてのフランス軍首脳の対応の鈍さを思わせるものがある。そして首都への道が文字通りがら空きであることに突如気づかされても、彼らはただただ茫然自失となるばかりで抵抗の術を知らなかった。そして間もなく電撃戦全体のクライマックスが訪れる。
「D+15日」、ついにIMFは韓国の経済的首都への入城を果たして実権を掌握、韓国は実質的に降服した。「準経済大国」であったはずの韓国のあっという間の壊滅は、電撃戦の矛先が本格的にそこに向かってから僅か2か月程度のことであり、無形化時間ならたった「1週間」の余りにも劇的な敗北であった。
これは韓国のみならず世界中にとってあまりにも大きな驚きだった。韓国はつい先日まで国内総生産世界11位の、押しも押されもしない経済大国ではなかったのか?それがこれほど瞬く間に壊滅するなど夢想だにしないことであり、この時の韓国人のショックは、恐らく1940年にフランス人が味わったそれに比肩しうるものではなかったかと思われる。
このそしてその後すぐに金大中が大統領に就任したが、彼の最初の仕事は、緊急融資要請によって経済的首都に進駐してきたIMFの占領軍を、経済敗戦国の指導者として迎えることだった。そして早速IMFは占領軍としての活動を開始し、かつて韓国が外資侵入阻止のために張り巡らせ、一時はマジノ線の如き頑強さを誇っていた様々な制度的防壁は、内側からIMFによってがらがらと撃ち壊されていった。
電撃戦の総決算
電撃戦は終わった。結果は決定的だった。実際もし仮にそれが明確なプランのもとに進められた作戦だったとしたならば、それは迅速性と結果の決定的な点において、経済戦争史上においてほとんど未曾有の成功した作戦だったと言えるだろう。
制圧されたこれらASEAN諸国の経済規模は、侵攻前には合計GDPが約1.3兆ドルだったのであり、これは東欧諸国(ロシアを除く)全体のGDPの3倍にのぼり、またフランスのそれにほぼ等しかった。
ところが通貨の暴落により、ドル表示でのGDPが一挙に半分から、国によっては1/4にまで減少、つまり経済的国土の半分以上がこの電撃戦で失われたのである。
米国以外では世界最大の成長センターと目され、その名をほしいままにしていたこの地域のたった「3週間」での壊滅は、その迅速さと規模の点で恐らく第二次大戦の西方電撃戦によるパリ陥落の例に比肩するものである。さらにそれは、準四次大戦の開始から無形化時間で「9〜10か月」後に起こったという点でも、奇妙な符合を見せている。つまりかつてのパリ陥落も、ポーランド電撃戦による第二次大戦勃発からちょうどそのぐらいの期間をおいて起こっていたからである。
この過程で為替金融帝国の人間たちが莫大な戦利品を手にしたことは言うまでもないが、米国の得たものも大きかった。その最大の成果は、まずアジア側の情報制空権の拠点をほとんど潰すことに成功したことだろう。
準四次大戦の開始の時点では、米国はまだ衰退の運命から逃れることができず、経済が主力となる無形化された次の大戦争においては、いずれアジア経済の追い上げに会って苦戦、敗退の道を歩まされるものと信じられていた。
ところがその難敵と見なされていたアジア経済をこれほど電撃的に粉砕し、またIMFの占領軍を送って中枢部を自側に有利な体制に変えることができたわけだから、もはや米国衰退論の論拠は最後の一つに至るまで陥落したことになる。
そしてこの事件の決定的意義はそれにとどまらない。そもそもアジア経済は、世界中の、これから経済発展をしようと考えている国々にとっての希望の象徴だったのである。ところがそれがここまであっけなく壊滅し、しかもその挫折がもし宿命的なものだったとすれば、もはや経済大国への道は新規参入を許さないものであり、その門が彼らにはすでに閉ざされていると宣告されたことを意味する。そういった意味でこれは単なる一地域の経済的混乱にとどまらない、世界史的影響を持ちかねない大事件であった。
ともあれ準四次大戦初期、一時は5大経済圏(米国・欧州・日本・中国・東アジア)の一角を構成するはずだと言われたこともあるこの地域は、序盤であっけなく戦線から脱落してしまったのである。
しかしながら帝国側の凱歌もそう長くは続かなかったようである。98年の8月になって、以前から駐屯していたロシアにおいてIMFの統治が破綻を来す兆候が見え始めたからである。
ソ連崩壊および準三次大戦の敗北以来、茫然自失の状態にあったロシアには、早くからIMFが駐屯しており、それはアジア方面の場合に比べると「平和的進駐」だったが、その統治にはもともともともと問題があり、それがこのとき一挙に表面化したのである。
予想外の場所で混乱が生じたことによって、成功の絶頂にあった「為替金融帝国」にも動揺が走った。また米国においても、さしもの初年度大攻勢の勢いも終着点に達し、力も衰える気配が見え始めている。恐らく今後米国は、その衰えを相殺すべく、ますます情報制空権への傾斜を強め、そして戦略全体も次第にB軍集団に主力をシフトさせていくのではないかと考えられる。
TOP