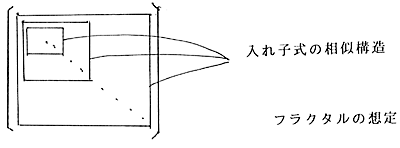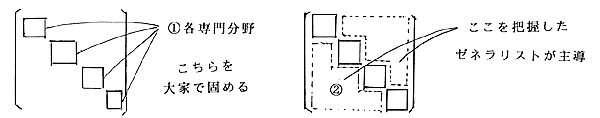複雑系に騙されないための「査定法」
※この稿は、複雑系の実態がどういうものかについて論じたもので、「物理数学の直観的方法 第2版」241ページあたりにつける予定だったものですが、分量が少々多いうえ、批判めいた色彩がかなり強くて本に収録するのはやや難があると思えたため、削除した部分です。
(20001105 長沼伸一郎)
・複雑系の大問題
・組織構成から診断する研究機関の実力
・複雑系で嘘をつく法
・実際の診断例--サンタフェ研の場合
・意外に大きいその影響
・日本は何をすべきか
§複雑系の大問題
こうしてみると、このように三体問題のところで角を曲がり間違えて、長年にわたって文明の上に何層にも積み重ねられてしまった部分の大掃除こそが、本来の正しい意味での「複雑系」に与えられた最大の役割だったはずなのである。ところが問題が大西洋を渡って90年代に米国でそれが華々しく登場したとき、そのセールス・ポイントの筆頭付近に来ていたのが「株価予測の新兵器に使える」などの点だったというのだから情けないというか何と言うか、一体全体世の中どうなっているのかとも言いたくなる。
それを別にしても、この時世間に大量に出回った複雑系の解説書を読んだ人に感想を尋ねると、どうも何かどこかで胡麻化されているようで今一つ納得できなかったと不満を洩らす人々が少なくないのであり、実際中には半ば憤慨しながら、あれはいんちきなのではないかと公言する人までいる有様である。
しかし裏事情を暴露すれば、この感想はかなり正しいのである。実際、複雑系に対するもやもやした印象は、次の一点について知ればあらかた氷解することだろう。すなわちそれらは多くの場合、本来あるべき方法とは逆の方向を向いて、出るはずのない結論を無理矢理引き出そうとしていた疑いが濃いからである。(そしてそういう場合、書き手自身が心情的あるいは立場的な理由で、ハーモニック・コスモス信仰に無理矢理しがみついていた可能性が高い。)
つまり本来これに対する正しいアプローチがあるとすれば、以前から何度も述べているように、まず「近代は何を誤解し、何ができないか」を徹底的に洗い出すことで、ちょうど迷路の「塗り潰し法」のように袋小路を残らず黒く塗り潰し、それによって道を白く浮かび上がらせることにあったはずである。
ところが90年代からの複雑系は、単に戦術的な道具だけの革新で今まで通りのアメリカ的な進歩をもっともっと続けようという思想のもと、背丈に合わない無理な期待のもとに世の中に送り出されたかの感がなくもない。
まあ「夢よもう一度」という研究者の心情もわからなくはないが、しかし当面これで迷惑するのは、良識を持った学芸部のジャーナリストなどであろう。実際インタビューした研究者の言うことを真に受けて記事や本を書いたら、十年ぐらいして赤面するような内容の代物になったというのではたまったものではあるまい。そこで、どういう場合なら信用できてどういう場合なら信用できないかの簡単な判定法を、以下にご紹介しよう。(故にこの部分は、マスコミの学芸部の方など必読である。)
しかしこの場合、面倒な議論をするよりも、むしろその研究をしている研究機関の組織や人事の方を見れば大体その将来を外から占うことができるのであり、まずそれを紹介しておこう。
この場合、注目すべきポイントは次の一点である。先ほど数学者と哲学者の間のエアポケットに盲点が生じた話をしたが(240ページ)、実にこれこそ複雑系研究の最大の問題である。
これに関しては、194ページでも、例えば社会を10個ぐらいの専門分野に分けて調べる場合、経済だけの専門家と軍事だけの専門家がそれぞれ作る小行列のN乗は、全体のN乗に一致しないことが示されており、このことから組織設計の重要な原則が導かれる。
すなわちこの場合、たとえ狭い各専門分野についてのみ通暁した専門家をいくら大勢揃えていたとしても、それら全部の要点をよく把握したゼネラリストが最低一人はいて、後者の発言力が前者より優先していない限りは、ほとんど無意味だということなのである。
実際こういう場合、問題をいくつかの専門分野に分割してから調べて後でつなぎ合わせることができないわけだから、たとえ作用マトリックスの①の部分をいくら各個に精密に扱えても、それらの相互作用たる②の部分を把握する能力をもつゼネラリストが主力となっていない限り、過去の分析も未来の予測も全く使いものにならないのである。
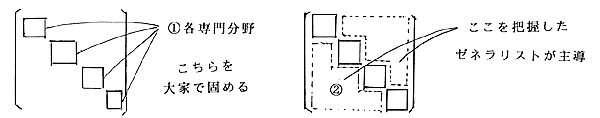
失敗する複雑系研究組織のパターン 成功する複雑系研究組織のパターン
つまりこの原則の理解は、ある意味で複雑系の本質と言えるのであり、複雑系を扱う以上は何らかの形でそれを可能とする組織形態を指向していなければならない。
逆に言えば、組織設計の段階でこの原則が軽視されていたとすれば、それはその組織全体が実は複雑系の本質をわかっていないことを示す一種のバロメーターになるのであり、このことを自分の設計にすら活かせないようでは、どんなに凄そうな「複雑系の専門家」が揃っていて難しそうな論文がたくさん書かれていたとしても、その組織はがなしうることは断片的・末梢的な技術の議論で終わってしまう可能性が高い。
そしてこれを踏まえると一つの皮肉な結論が導かれることになる。それは、ある複雑系研究機関なり学際研究シンポジウムなりが、最初に地位名声の高すぎる単分野の「専門家」の大先生を大勢集めてしまうと、皮肉にももうそれだけでにっちもさっちも行かなくなってしまうということである。
なぜならこういう場所には、その大先生たちのばらばらな発言力を抑えられるゼネラリストが存在できなくなる。そしてこれからそういうゼネラリストを育てていこうとすれば、その組織はどこかで両者の権力逆転を経験せねばならず、集めた大先生たちの面子を片っ端から潰した挙げ句、予算まで取り上げていかねばならない。そんな修羅場は誰もが避けたいし、どうせゼネラリストの絶妙な通訳がなければお互いの発言内容もわからないのだから、可もなく不可もない最大公約数的なことを適当にアカデミックな単語で装飾したレポートでも出して、お茶を濁すことに終始しがちなのである。
つまり皮肉なことだが、この種の研究組織を設計する際には、むしろそれら大勢の各単一分野の専門家に関しては、むしろ実力や知識は十分にある割には学内での地位が低くて冷や飯を食っている無名の若手で構成しておいた方が、まだしも将来の発展の余地が残りやすいと言えるかもしれない。
ともかく結論を整理すると、この種の研究組織を診断する際には、まずゼネラリストとして全体を総覧する立場にある人物や部署がどこにあるかを探すことである。ただし現在の状況ではそういう部署は、ちゃんと役割を果たせば果たすほど何らかの形で周囲の制度や習慣との間に摩擦を生じる宿命を負っており、そしてそこが結局は組織全体の能力を決めてしまうわけだから、要するにそこが周囲との間にどの程度の緊張を抱えているかを見れば、大体その研究組織の将来性はわかってしまうと思って差し支えないだろう。
ところで昔「統計でウソをつく法」(講談社ブルーバックス)という面白い本があって、統計の専門家たちが使う騙しの手口を実例とともに面白おかしく紹介していたが、複雑系もまたそういうことの激しい場所で、それゆえその基本的な手口を少しだけ以下に紹介しておこう。
そもそも何度も言うようだが、複雑系の正しいビジョンが頭に入っていたときまず第一に見えてくるのは、いかに近代が多くのことを安直に「できる・わかる」と錯覚していたのかということであり、そのためもしこの迷宮から何らかの意味のある情報を引き出そうと思えば、そういう安直な錯覚の部分を最初に徹底的に塗り潰してからでなければ話が始まらない。袋小路の塗り潰し方が不十分では、迷路の通り道はまず浮かび上がってくるものではないからである。
そのため逆に言えば複雑系で嘘をつく場合、まずこの作業を甘くしておくことがステップとして重要である。それゆえ最初になるたけたくさん目眩ましに薔薇色の話をちりばめて雰囲気を盛り上げておくことが必要であり、逆に、米国流の文明がいかにハーモニック・コスモス信仰の上に立っていたかなどという話は、ヤブ蛇になるので最初から行なわないほうが賢明であろう。
そして次に手口の核心となるのは、ありもしない均一性を話の中に勝手に仮定し、そしてそういう仮定を置いているということを巧妙に黙っていることである。
もともと昔の数学や合理主義があれだけ威力を発揮したのは、もともと研究対象自体が非常に均一な性質をもっていたからであり、逆に言えばそういう均一性(あるいは作用マトリックスのゼロ成分や共通細胞の存在)を勝手に仮定することが許されさえすれば、いつだって物凄い威力のある数学を作れるのである。
複雑系におけるそういう想定の実例について言うと、いわゆる「フラクタル理論」などはその一例であり、そこでは入れ子式の相似構造、つまり絵の中の部屋の壁にかかっている絵を拡大するとそれが全く同じ絵でそれが延々と無限に続く、というような一種の共通性が想定されている。
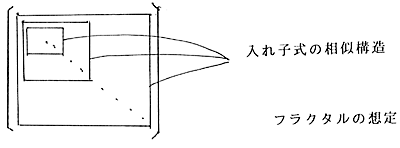
そのためそこをいわばテコにする格好で、コンピューター・グラフィックスなどにいろいろ応用が効くわけだが、ところがこれが登場した当時(よせばよいのに)調子に乗って、これを使うと今までわからなかった自然界のいろいろな現象の謎が解明できるというところまで話が行ってしまっていた。
しかしそこまで言っては過剰宣伝であるということは、この判定法から容易にわかるだろう。なぜならこの概念はそういう特殊な(半ば人為的な)共通性がもともと存在しない一般の系には最初からお呼びではないからであり、理学部での使用にはがっかりするほど小さな威力しかもっていないのである。
つまりもしある研究者が、複雑系のこういう難しい数学を使うと凄いことがわかる、とやたらに薔薇色の話を主張しているのだがどうも何だか怪しいという場合、こちらは作用マトリックスを頭に思い浮かべ、それではあなたが問題にしている系は、どこに均一性(あるいは共通細胞、ゼロ成分)が想定されているのですか、と問えばよい。
もし相手の言うことが掛け値なしの真実なら、どこかに必ずそういう条件や適用限界が想定されているはずであり、質問に対して相手がにやりと笑って、実はね、とその種を明かしてくれるようなら、まあその人の話は信用しても良い。
それに対してもしその質問をした瞬間に、話が突然難しくなって一言もわからなくなったり、あるいはしつこく問い質したら気まずい空気が流れ出したりしたならば、多分どこかに何かを隠している可能性が高い。特に、質問への答えをいきなり中断して引き出しからグラフィックチャートなどをがさがさと引っ張り出し始めた場合、それは返答に詰まって必死に時間稼ぎをしているためであることが多く、その人の話を全部信用するのは避けた方が賢明である。
まあとにかく複雑系にはこの手の話が多く、例えば株価の暴落のような現象を複雑系の数学で予測するなどという話の場合にも、どこかにそういう人為的な仮定がない限りは実際には話として成り立たないはずであり、騙されないように注意が必要である。
ただいずれにせよ言えることは、この複雑系という特殊な分野に限って言えば、近代とハーモニック・コスモス信仰の関係という、いささか数学よりも歴史哲学のような議論がベースにない場合、とかく迷路の塗り潰し方が不十分になりやすく、そのためこれが欠けているとどうしても断片を一枚の絵にすることが難しいようである。
そして以上に関する実際の診断例を挙げるとなると、どうしても複雑系の代表選手として名乗りを上げたサンタフェ研をとりあげざるを得ないことになるが、どうもここがやっていることを見ていると(別にここを目の仇にしているわけでもないのだが)、まさに以上に述べた「べからず集」を、まるごと実践しているかの感がなくもないのである。
まず、ここは別に米国の国策機関として作られた組織ではないが、それでもやはりその精神は米国の理念に忠実に「もっとわかってもっと進歩する」理論を作ろうという方向性のもとに作られており、逆に言えば「何ができないかを直視する」ことにはあまり熱心でなく、とかくそういう話は「臭いものに蓋」をしがちな傾向がある。
当然そうなると、近代とハーモニック・コスモス信仰のかかわりなどという話題はそこでの議論から遠ざけられるであろうことは想像に難くない。そのため(われわれの診断法に従う限り)、複雑系それ自体に関しても、迷路の塗り潰し方が不十分である以上、断片的な理論はたくさん作れてもそれらを一枚の絵にすることがなかなかできにくくなる宿命を抱え込むことになる。
そしてまた組織の設計の面でも、まさしく先ほど述べた禁止事項がほぼそのまま実践されている。それというのも、ここは立ち上げに際して各専門分野のそうそうたるメンバーを世界中から集め、それゆえ当時大変に話題になったのだが、一方それに対して、彼らを統合指揮できる人物をどうするかについては関心が薄く、そういうゼネラリストのビッグネームは不在で、異分野の各専門家の橋渡しをする「翻訳者」さえ置かれていなかった。
そのためちょうど作用マトリックスのN乗不一致の法則の見本のようなことが起こっても不思議はない状況にあったわけで、現実に状況はまさしくその通りのものになっていたようである。
つまり、各分野の専門家たちを一か所に集めたは良いが、それはちょうど英語以外しゃべれない英文学の専門家と、日本語しかしゃべれない日本文学の専門家をしばらく同じホテルに泊まらせれば、それだけで素晴らしい英和辞典ができると期待するようなものだった。
とにかく各専門家たちは互いに何を考えているかを真に理解することができず、断片的な単語の交換以上のことはできなかったのである。実際作用マトリックスのイメージが頭にあれば、単に彼らを一か所に集めて歓談させたぐらいで全体がわかるようになるほど、世の中は甘くないということは一目瞭然であろう。
そしてこうなってくると話は、一体全体そもそも彼らは本当に複雑系の本質を理解していたのかというところまで行かざるを得なくなってくる。それというのも、枝葉の部分はともかく、幹に当たる肝心の部分を本当に理解していたとすれば、最初からああいう形で組織の設計を行なうはずがないのである。
ところが最初の設計がそのようだった上に、終始その設計の欠陥に対する批判が内部から起こっていなかったというところを見ると、どうもこの面からもその研究活動自体が、実はこの一番単純な本質を理解しないまま末端の技術だけをばらばらに磨いていたに過ぎないのではないかという疑いにつながってくるわけである。
この疑いを裏書きするもう一つの材料として、次のようなことがある。それは本来なら、現在議論の的になっている遺伝子操作が安全か危険かの問題こそ、ある意味で複雑系という学問にとっての絶好の舞台であるはずだということである。
それゆえもしこれについて何か少しでも語るべき研究内容のストックをもっていたとすれば(彼らの知名度をもってすれば必ずジャーナリズムが飛びつくことを期待できる以上)、何らかの声明を出すことは自らの存在をアピールするための、またとない絶好の機会だったはずなのである。にもかかわらずそれらしい声明がさっぱり聞こえてこなかったことは、どうも先ほどの疑いを裏付ける事実の一つである疑いが濃い。
(それに大体絶好の機会といえば、そもそも先ほど述べた組織設計の際のゼネラリストの不可欠性を、N乗不一致の法則の裏付けのもとに組織論としてまとめ、彼らの知名度に乗せて流布させれば、今頃世界中の企業のバイブルとなって講演料を荒稼ぎできたはずなのだが、やはり未だにそういうことは行なわれていない。)
思えばずいぶん奇妙なことになっているものだが、それが本当に理解の不十分から来ていたのか、それともサンタフェ研が設立時に一種、米国の夢の守護者としての役割を期待されていたため、今さらそれと逆行するようなことは言えなくなっているのか、そこのところはよくわからない。しかしいずれにせよこれは意外な重要性をはらんだ問題であり、それゆえ次のことは理系ばかりでなくジャーナリストの人々などにも是非知っておいていただきたいのである。
例えば遺伝子産業の問題を考えてみよう。現在、遺伝子組み替えの安全性を巡って米国と欧州などの間でも議論が対立しているが、何しろこれに関しては検証の手段が大仕掛けであるうえ、直観的に全体を見通すための方法もないため、外部にいる者にとっては当事者が提出する生情報を鵜呑みにするほかなく、実態が曖昧なまま言葉だけが空回りして、とかく政治のみの水掛け論になりやすい。
ところがここに、大学の教養過程の数学ぐらいで修得できる手法で、精度はさほどではないが、こういう複雑な系では何をやると危ないのかを、かつての初等解析ぐらいの手軽さで直観的に把握できるという手法があったとしたらどうだろう。
実際そういうものが一般技術者やエコノミストにある程度普及して、その論争の中に投げ込まれた状況を想像すると、恐らくそれらに関する議論や国際会議などの進められ方は、現在とは相当に異なってくる可能性が小さくないのである。
そしてもしそれが遺伝子産業ばかりでなく、IT産業の影響を直観的に見通すことや、特許がどこまで及んでよいかを判定する問題にも応用できて、それらに関するある程度の目標数値を算出することができたとしたならば、これはまさに国家的問題である。
もっともこの場合、そういう使いやすい解析手法が登場したことで、得をする国と損をする国が出て来ることになるのは当然である。例えば米国の場合、先行組の優位というものを手にしている以上、遺伝子ビジネスにせよIT文明にせよ、うるさい規制なしに無制限にそれらを前進させることが国益にかなうのであり、逆に言えばそれに待ったをかけるような、使いやすい解析手法が登場することは邪魔なのである。
そして日本の場合には言うまでもなく立場がちょうど逆で、もしそういうブレーキに使える手法を本当に普及させることができれば、遺伝子産業で出遅れたことなど何ら恐るるに足らない。
例えばすでに米国ががっちり囲い込んで既得権としている大量の遺伝子特許の何割かについて、その危険性を数学的に証明して世界中の一般技術者の賛同のもと、無効に追い込むことさえ場合によっては可能となるわけで、ここは出遅れ組の日本などにとっては本来、国家的関心がもたれてしかるべきところである。(ただし無論、このことに気づいている政策担当者は恐らくまだ誰もいないではあろうが。)
ともあれこのように話の断片を組み上げてみると、それは意外にジャーナリスティックな関心を呼ぶ話になっていることがわかる。
すなわち、もし90年代からの米国の複雑系が、本来この学問に期待されるのとはあべこべの方向に向かったためにそれが一枚の絵にならず、そしてサンタフェ研などがその権威として居座ったため、ちょうど「てっぺんに重しを乗せる」格好で、その本来の発展を世界全体で停滞させ、結果的にそれが遺伝子産業などで先行する米国の国益を当面守ることに役立っていたとしたらどうだろう。
そしてここで問題になるのは、本来鍵を握る立場にあるはずの日本の大学の対応である。つまりもしここで従来のように、「欧米でのお墨付きが出るまでは一切動かない」という日本の大学の伝統的姿勢が如何なく発揮されたとすれば、日本から独自の動きが出て来ることはなく、そのため後になって振り返るとこれまた過去に何度も繰り返されたように、結局この件で一番駄目だったのは日本ではないか、との非難を浴びかねないという、何ともしまらない話になってしまう。
本当を言えば、外からジャーナリズムの応援を頼まねばならないとするならば、それは物理学者たちにとって何とも不面目な話ではある。しかし困ったことに今の大学というところは、仲間うちの狭い世界で褒め合っておりさえすれば論文は出続けるし、外から攻撃を受けることも滅多にないのである。
そのためこの件に関する限り、良識派のジャーナリストがきちんと自分の目で、本当のことを言っているのは一体誰なのかを判断することは極めて重要なのである。そしてその際に一番良いのは、複雑系で飯を食っている「権威」の先生に話を聞くより、むしろ(直接はそれで飯を食っているわけではない)一般の理系の人々の広範囲な感想を集めることであろう。
そのため文系のジャーナリストならば、高校時代の同級生の名簿の中から理系進学組を当たって、旧交を温めつつ裏から感想を聞いてみるというのが、存外一番良い方法なのかもしれない。